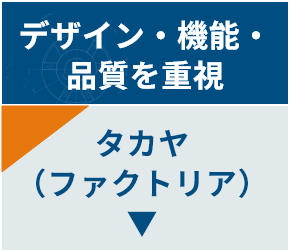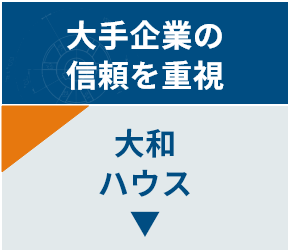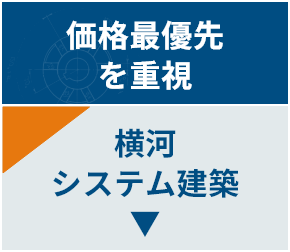事業継続計画の一環として考えるべき耐震補強とその費用 | 工場建設パーフェクトガイド
工場建設の情報
事業継続計画の一環として考えるべき耐震補強とその費用
公開日:2025.01.26 更新日:2025.02.28

企業にとって事業継続計画(BCP)の策定は不可欠であり、自然災害やシステム障害などのリスクに対応するために事前の準備が重要です。特に日本では地震対策が必須であり、建物の耐震補強や従業員の安全確保が求められます。
工場では古い建物の耐震性が課題となるため、専門家による診断や適切な補強が必要です。耐震診断は予備調査と本調査の二段階で行われ、費用は建物の構造によって異なります。
高品質な工場建設を目指す場合、耐震性を重視した建設会社の選定が重要であり、タカヤ、ガンコ建築、システムハウスR&Cなどが耐震技術を活かした工場建設を提供しています。
目次
BCP(事業継続計画)の重要性と企業に必要な対応策
自然災害や突発的なリスクに対応するため、企業にとって事業継続計画(BCP)の策定は不可欠です。BCPは、緊急時に事業をどのように維持・再開するかを明確に定めた計画書であり、企業のリスク管理において中心的な役割を果たします。
◇企業のリスク管理とBCP
企業のリスク管理は、将来予測可能なリスクに備え、発生時に迅速かつ適切に対応することを目的としています。
BCPは、事業活動が中断された際に、その影響を最小限に抑えるために策定されます。自然災害、システム障害、パンデミックなど、さまざまなリスクに対応するためには、事前の準備が極めて重要です。
具体的には、サプライチェーンの断絶に備えて代替供給元を確保することや、情報システムのダウンに備えてバックアップ体制を強化することが求められます。
◇耐震対策の重要性
日本は地震が頻発する地域であるため、企業にとって耐震対策はBCPの重要な要素です。特に、地震による建物や設備の損傷は、企業の運営に重大な影響を与える可能性があります。
耐震性が不十分な建物での作業は、従業員の安全を脅かすだけでなく、企業の信頼性にも悪影響を及ぼします。このため、BCPには建物の耐震補強や施設内の重要設備の耐震対策が欠かせません。
さらに、地震時に事業継続に必要なリソースを確保するために、重要なデータのバックアップ体制や代替オフィスの準備も重要です。従業員の避難計画を整え、地震発生時に安全かつ迅速な避難が可能となるよう、定期的な訓練を行うことも欠かせない対応策です。
耐震補強が必要な工場で確認すべきことは?

工場やその他の施設では、耐震補強が必要な場合、どこを重点的にチェックすべきかを把握することが重要です。特に古い建物は、現行の耐震基準に比べて弱点が多く、適切な対策を講じる必要があります。
◇40年以上経過した建物
耐震設計基準は1981年に大幅に改定され、それ以前に建てられた建物は現行基準と比べて耐震性が劣る可能性が高いです。特に40年以上経過した建物では、建設当時の基準が現在の基準を満たしていないことが多く、耐震性が不十分であるリスクがあります。
そのため、古い工場の場合、構造図や設計図を基に現行の耐震基準に照らした評価を行う必要があります。また、経年劣化により建物の強度が低下しているおそれがあるため、専門家による詳細な耐震診断を受けることが重要です。
◇見えない劣化をチェック
建物構造の劣化は、確認が困難な場合が多く見られます。特に鉄筋コンクリート構造の工場では、コンクリート内部で鉄筋の腐食やひび割れが進行していることがあり、これらは目に見えないため、専門的な耐震診断が必要です。
例えば、湿気や温度変化の影響で鉄筋が内部で腐食している場合、外見上は損傷が見えなくても耐震性能が大きく低下している可能性があります。劣化の早期発見と修復・耐震補強工事は、地震時の安全性を確保するために欠かせません。
◇1階の脆弱性に要注意
工場の1階部分は、上階の構造や設備の重量を直接支えるため、地震時には荷重が集中する場所です。このため、1階の基礎、柱、梁が十分に強固でない場合、耐震性に問題が生じる可能性があります。
さらに、工場の1階部分がソフトストーリー構造の場合も注意が必要です。ソフトストーリーとは、1階に大きな開口部(駐車場など)があり、柱や壁が少ないことで脆弱性が懸念される構造を指します。
ソフトストーリー構造の建物は、1階部分が柔軟に揺れやすい特徴を持ち、地震時の損傷リスクが高まります。このため、ソフトストーリー構造の工場では、1階部分の補強や強化が重要です。
耐震診断ってどう進める?工場・倉庫の費用
耐震診断は、建物の耐震性を評価し、必要な対策を講じるための重要なプロセスです。特に工場や倉庫などの施設では、業務を継続するためにも早期に適切な診断を行うことが求められます。
以下では、耐震診断の進め方と、工場・倉庫の診断にかかる費用の目安について説明します。
◇耐震診断の進め方
耐震診断は通常、「予備調査」と「本調査」の2つのステップで実施されます。
まず、予備調査では、建物において特に問題のある部分を抽出し、本調査に進むかどうかを判断します。この段階では、建物の構造や設計図書、過去の改修履歴などの情報を基に耐震性が十分かどうかの初期評価を行います。
本調査は、実際に建物を詳細に検査し、構造部材(柱、梁、基礎など)の状態を確認するプロセスです。確認の際には、ひび割れや劣化の有無を目で見て調べたり、専用の機器を使って部材の内部状態を確認したりします。必要に応じて、部材の強度を数値で評価することもあります。
◇耐震診断の費用目安
耐震診断の費用は、建物の構造によって異なります。以下にRC造(鉄筋コンクリート造)とS造(鉄骨造)の一般的な費用目安を示します。
・RC造(鉄筋コンクリート造)
耐震診断費用は、約1,000円/㎡~約2,500円/㎡程度が目安です。
・S造(鉄骨造)
S造では、耐震診断費用は約1,200円/㎡~約3,000円/㎡程度が目安です。鉄骨造の場合、接合部や鉄骨の状態を評価するために追加的な調査が必要となることがあり、その場合は費用が高くなることがあります。
高品質な工場建設を実現するおすすめの建設会社
高品質な工場建設を検討する際、耐震性は非常に重要な要素です。以下に、耐震性に重点を置いたおすすめの建設会社をご紹介します。
◇株式会社タカヤ
株式会社タカヤは、「Factoria」というブランドを展開し、機能性・安全性・デザイン性を兼ね備えた工場建設を提供している企業です。特に耐震性への取り組みは顕著で、地震が頻発する日本の環境に適した構造設計を採用しています。
同社の大きな特徴は、近年の工場に求められる機能性や優れたデザイン性を損なうことなく、制振技術や免震装置を適切に取り入れることで、地震の影響を最小限に抑える設計を実現している点です。
◇ガンコ建築株式会社
ガンコ建築株式会社は、創業以来40年以上にわたって工場・倉庫の建設を専門に行っている企業です。同社の特徴は、阪神淡路大震災を機に、建物の耐震性を再考し、柔軟かつ強固な構造設計と耐震技術を追求してきたことにあります。
特に評価されているのは、同社の「耐震診断サービス」と「耐震補強設計」です。診断では、建物の脆弱性を細かく調査し、補強が必要な箇所を的確に洗い出します。さらに、地震時の被害を軽減するために、免震装置や制振ダンパーの導入を提案することも可能です。
◇株式会社システムハウスR&C
株式会社システムハウスR&Cは、モジュール型の工場建設を得意とする企業です。同社は、設計段階から耐震性を考慮した部材選定を行い、揺れに耐える頑丈な構造を提供します。
また、地震リスクが高まる現在の環境において、建物全体が地震エネルギーを効率的に分散させる設計手法を採用している点が特徴です。
さらに、同社は地震発生後の復旧を迅速に行うための設計にも力を入れており、事業活動を長期間中断しない建物作りを目指しています。
企業が事業継続計画(BCP)を策定することは、持続可能な経営を維持するうえで極めて重要です。地震や台風、火災、システム障害など、企業活動に影響を与えるリスクは多岐にわたり、これらに備えるためには事前の準備が欠かせません。
特に日本は地震大国であり、企業の安全対策として建物の耐震補強や従業員の避難対策が求められます。製造業をはじめとする工場では、老朽化した建物の耐震性が課題となることが多く、地震発生時の被害を最小限に抑えるためには、専門家による診断と適切な補強工事が不可欠です。
耐震診断はまず予備調査を行い、その後、本調査によって建物の具体的な耐震性能を評価します。診断結果に基づき、補強方法やコストが決定されます。
工場の新設や改修を検討する際には、耐震性を重視した建設会社の選定が企業の将来を左右します。耐震技術に優れた建設会社として、タカヤ、ガンコ建築、システムハウスR&Cなどが挙げられ、それぞれの企業が培ってきたノウハウを活かし、安全で信頼性の高い工場建設を提供しています。